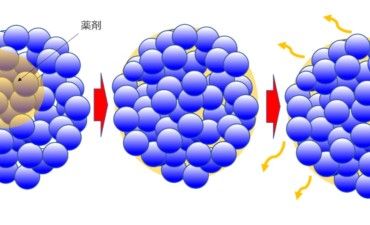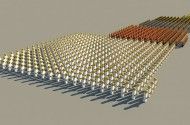コミュニティ新着投稿
Seminars
新着セミナー
2024年 06月 20日 (木)
13:00 - 17:00
申込締切 2024年06月12日
滅菌工程に関わる監査対応の準備はできていますか?事例を踏まえて、EO滅菌装置の導入、バリデーションについて解説しますISO11135の改訂についても当日わかる範囲にて解説いた...
2024年 06月 27日 (木)
10:30 - 16:30
申込締切 2024年06月19日
QA担当の役割は適切に判断を行うこと、それには経験が必要となります講師の実体験からQA担当者としての『品質課題の判断力』を習得しましょう ●申込締切:2024年06月19...
2024年 06月 27日 (木)
10:30 - 16:30
申込締切 2024年06月19日
本セミナーではサンプルサイズ計算理解に必要な統計学について説明した上で、統計手法ごとに、サンプルサイズの計算原理とともに、RやExcelを用いたサンプルサイズの具体的な計算方...
2024年 06月 26日 (水)
10:00 - 16:30
申込締切 2024年06月18日
大好評リピート開催!分バリの実施には統計の知識が欠かせませんが、苦手...という方も多いですよね ※本セミナーは、+9,900円(税込)でアーカイブ配信のオプション申込が可...